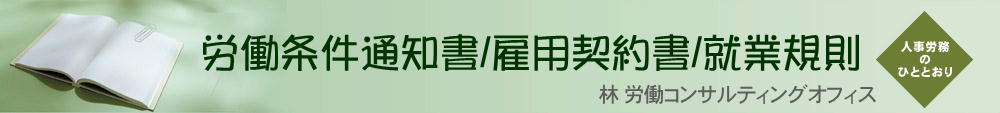労働条件通知書と雇用契約書
労働条件通知書は労働基準法で明示を義務づけられた事項の一部または全部を書面化した物で、書面による明示を義務付けられた部分については書面で交付しないと罰則があります、これに対して雇用契約書は労働契約法で出来れば文書で取り交わす事が望ましいとされているもので、文書を取り交わさない事に対する罰則などはありません
それなら労働条件通知書だけで良いか?というと、そうとも言えません、就業規則も未整備な若い事業所などでは特に労働条件通知書以外に取り交わしておきたい約束事も多いはず、人事管理の第一歩として熟慮の上、良い契約書を作成し後日のために労使双方で記名押印をして、取り交わしておきましょう。
雇用契約書の書式・内容は自由ですので労働条件通知書の書面による明示事項を完全に取り込んで兼用とすることもできます。
労働条件通知書には以下の書面による明示条件を記載し、書面受渡と同時に口頭でも良いとされる明示条件について通告すれば良い事になります、(口頭でも良いとする明示条件はその内容を見ればわかるように、事業所によって制度が有ったり無かったりする事項が中心ですが、雇用する労働者に適用する制度があれば後日トラブルにならないようにこの部分も書面化して渡しておく方が良いでしょう、書面による明示条件の⑺~⑽まではパートタイマーに対してのみ通知義務のある特定事項です、そうですパートさんを雇った場合にも労働条件通知書は必要です、雇用形態を「有期雇用」とした場合は「契約更新」にともなう条件も通知しなければなりません。
労働条件通知書で明示すべき労働条件
書面による明示条件 |
口頭でも良い明示条件 |
| ⑴労働契約の期間の有無、期間の定めの ある労働契約については更新の有無及び その判断基準 |
⑴昇給に関する事項 |
| ⑵有期雇用特別処置法による特例対象者の 無期転換申込権が発生しない期間 (上記有期労働者を雇用をする場合) |
⑵退職手当の定めが適用される労働者の 範囲、退職手当の決定、計算・支払 いの方法、支払い時期に関する事項 |
| ⑶就業の場所・従事する業種の内容 | ⑶臨時に支払われる賃金、賞与などに 関する事項 |
| ⑷始業・終業時刻、所定労働時間を超え る労働の有無、休憩時間、休日、休暇、 交代制勤務をさせる場合は就業時転換 に関する事項 |
⑷労働者に負担させる食費、作業用品 その他に関する事項 |
| ⑸賃金の決定、計算、支払いの方法、賃 金の締め切り・支払いの時期に関する事項 |
⑸安全、衛生に関する事項 |
| ⑹退職に関する事項(解雇の事由を含) | ⑹職業訓練に関する事項 |
| ⑺昇給の有無 | ⑺災害補償、業務外の傷病扶助に関す る事項 |
| ⑻退職手当の有無 | ⑻表彰、制裁に関する事項 |
| ⑼賞与の有無 | ⑼休職休暇に関する事項 |
| ⑽短時間労働者の雇用管理の改善に関 する事項に係る相談窓口 |
雇用形態別に 必要事項を網羅した、労働条件通知書のひな型が労働基準監督署などで入手できます労働条件通知書のみの交付で済ます場合、はこれを使うのが必要事項の漏れも無く勘所も抑えてあり安心です(自分の会社に本当に適合しているかどうかのチェックは忘れずに)。
就業規則に当該労働者に適用される条件が具体的に規定されている場合は、契約締結時に労働者 1人1人に対し、その労働者に適用される部分を明らかにしたうえで就業規則を交付すれば、再度、同じ事項について、労働条件通知書として書面を交付する必要は無いとされていますが、実際にこれを毎回やるとなるとかなり面倒くさい作業です、実務的には要点整理をかねて雇用契約書なり労働条件通知書を作成した方が早いでしょう。
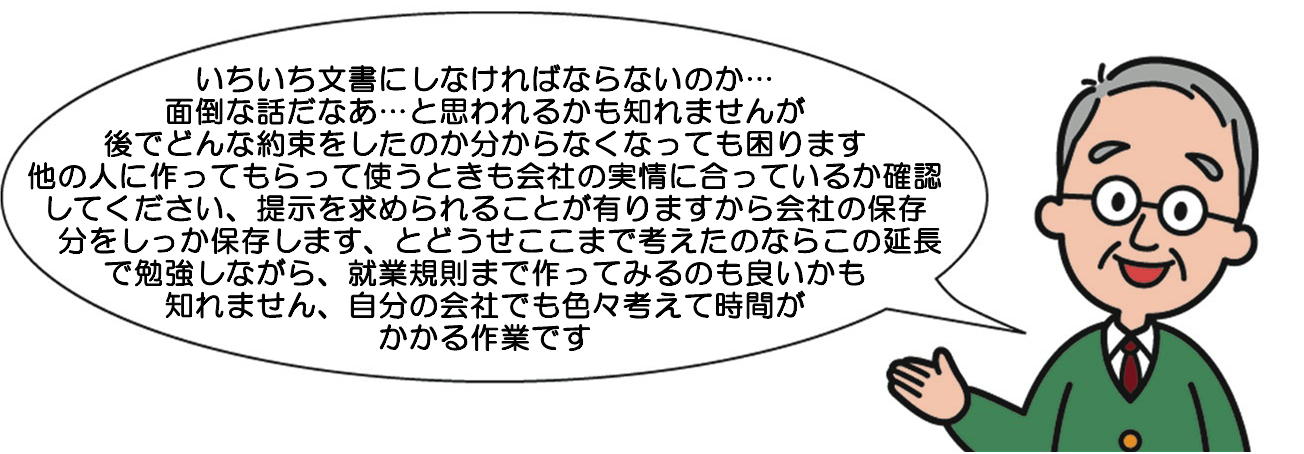
雇用契約書から就業規則への発展を考える
雇用契約書を取り交わしたらその考え方をベースに就業規則を考えてみませんか?常時10人以上の労働者を雇用する事業所のの使用者は就業規則を作成して労働基準監督署に届出る義務があるので、その場合は待ったなしですが、10人未満の事業所なら人事労務のひと通りを見て行く意味でも時間をかけて整備してみるのも良いかもしれません,
私の所でも就業規則作成に結構なプライスをつけていますが、作業時間を積み上げると一般的にはその程度の価格になる作業ですので、ひと勉強するつもりで取り掛かってください。
就業規則の必要記載事項は以下の表のとおりですが、他にも取り決めておきたい事項は多いでしょう
労働基準監督署や都道府県の労働関係窓口ではモデル就業規則を資料として配布している所もありますからこれを土台に就業規則を作成するのはお勧めです、作成に当たって疑問点や出来上がった就業規則の点検もそれぞれの配布していた官署の窓口で相談できる場合も多いでしょう、作成者は事業主本人ですから案外スムーズに作れたりする部分もあります。「厚生労働省のモデル就業規則は労働者に都合の良い事ばかり書いてあるから、あれで就業規則を作る会社はひどい目にあう」という向きもありますが、労働法にも適合しない条項を百万遍書いたところで通用しない就業規則が出来上がってしまうだけです、
ひどい目にあうとすれば、モデル就業規則はひな形としてほぼ完成した就業規則の体裁をとっているため、内容をよく理解せずに自社の就業規則としてしまった場合です、これは厚生労働省のモデル就業規則に限らず社労士などに依頼して作成させた就業規則等であっても、疑問な点についてよく説明を受けることなく受け入れてしまった場合等には同様の危険がありますからご注意ください。
就業規則は各事業所の事情に合わせて手を入れて、十分理解した上で行政相談や社会保険労務士に点検してもらって下さい、そこまでが就業規則の作成時間です。出来上がった就業規則は次のような方法で全従業員に周知します。
就業規則の周知方法
1.常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける。
2.書面を労働者に交付する。
3.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録 の内容を常時確認できる機器を設置する。
10人以上の事業所の場合は従業員の過半数を組織する労働組合がある時はその労働組合、労働組合が無い時は従業員の過半数を代表する者の意見を聴取した意見書を添えて労働基準監督署に届け出る必要があります(従業員代表者は課長などの管理監督者であってはならず、きちんとした選挙等でで選ぶ必要があります)。
届け出を急ぐあまり社長が以前在籍した会社の就業規則をそのまま届出して、後で困った事になった例もあります、自社に適合しているかしっかり点検してください。
就業規則の必要記載事項
| 絶対的必要記載事項 就業規則には必ず記載すべき事由 |
相対的必要記載事項 何らかの定めをするなら必ず記載すべき事項 |
| ⑴始業及び終業の時刻、休憩時間、休日 休暇並びに労働者を2組以上に分けて 交替に就業させる場合においては、就 業時転換に関する事項 |
⑴退職手当の定めをする場合におい ては適用される労働者の範囲、退職 手当の決定、計算及び支払の方法並 びに退職手当の支払の時期に関する 事項 |
| ⑵賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項に おいて同じ。)の決定、計算及び支払の方法 賃金の締切及び 支払の時期並びに昇給に関する事項 |
⑵臨時の賃金等(退職手当を除く。)及 び最低賃金額の定めをする場合におい てはこれに関する事項 |
| ⑶退職に関する事項(解雇の事由を含む) | ⑶労働者に食費、作業用品その他の負担 をさせる定めをする場合においては、 これに関する事項 |
| ⑷安全及び衛生に関する定めをする場合 においては、これに関する事項 | |
| ⑸職業訓練に関する定めをする場合にお いては、これに関する事項 | |
| ⑹災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定 めをする場合においては、これに関する事項 | |
| ⑺表彰及び制裁についての種類及び程度に関す る事項 | |
| ⑻以上のほか、当該事業場の労働者のすべて に適用される定めをする場合においては、 これに関する事項 |