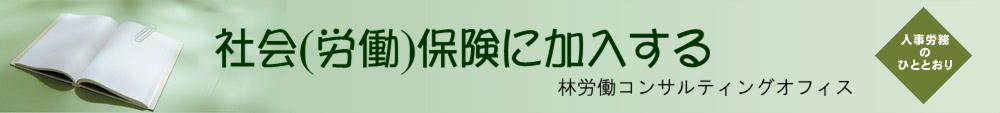労働保険・社会保険に加入する
「社保完」などと求人誌などでよく眼にする、労働者を雇用する企業が加入するべき公的保険である労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金の加入手続きです。
同じ公的保険でも労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金)に分かれているように、各保険ごとに微妙に加入させるべき労働者の範囲や手続きが異なっており、ちょっとだけ面倒です、それぞれの担当窓口か社会保険労務士などに尋ねながら進めてください。
各保険ごとに提出書類があり、従業員から書類を提出して貰ったり聴取して記入すべき事もそれぞれに存在します、要領良くまとめてやらないと、ひとつつ手続きするたびに「あれが足りない、これが不足」と伝言ゲームのような状態になってスムースに手続が進みません。アウトソーシング等している場合は更に一段階伝達する階層が増えるので混乱する場合もあります、求める記載や提出してもらう書類は要領よく一括して集め、手続してしまうのがコツです。
労災保険(労働者災害補償保険)
仕事中に起こった事故と通勤途上で起こった事故のうち業務災害と通勤災害にあたる災害を保証する保険で、パートやアルバイト等であっても、一人でも人を雇った場合はごく一部の例外を除いて加入する義務があります。
一般的な職場でも交通事故など思わぬ災害に遭遇するリスクはあるもの、労働災害は使用者の責任になります、労災保険に加入手続きがとられていなくても労災事故にあった労働者には労災保険から給付がなされますが、その場合故意または重大な過失によって加入手続を怠った使用者には重いペナルティが課されますから注意しましょう。
事業主は労災保険に加入できませんが、労働保険事務組合に加入するなど一定の条件のもとに加入出来る場合があります。
原則として一人でも従業員を雇ったら、保険関係成立届とその後に提出する労働保険概算保険料申告などを所轄労働基準監督署へ提出する事から手続きが始まります。
労働保険事務組合
金融・保険・不動産・小売業は常時50人以下、卸売り・サービスの事業では常時100人以下、その他の事業では常時300人以下の事業所の事業主が加入できます
労働保険事務組合に加入すれば上の保険関係成立届など労働保険に関する多くの事務手続きを委託できる他、金額にかかわらず労働保険料を分割納付できるようになり、使用者や家族従事者には労災保険加入の道が開けます。
雇用保険
俗に失業保険と言われているように雇用を失った時の給付を含む保険です、その他にも様々な雇用助成等も行っています、保険の性質上事業主は保険料の負担はしても被保険者にはなりません、しかし助成金は受ける事が出来ます。
原則として週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上継続して雇用される見込みの従業員は雇用保険の一般被保険者となります(この外にも高年齢被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者などの雇用保険被保険者となる場合がありますので、該当すると思われる場合はお問い合わせください。)
加入するには、雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届等を所轄の公共職業安定所に提出します
その際「労働保険の保険関係成立届(控)等」が必要ですから労災保険の手続き終了後に手続きすることになります。
(農林漁業や建設業の事業主さんは、雇用保険の保険関係成立届を別途公共職業安定所でも行う必要があり複雑です、該当すると思われる事業所の方は最初にアクセスした所轄労働基準監督署で尋ねると良いでしょう。)
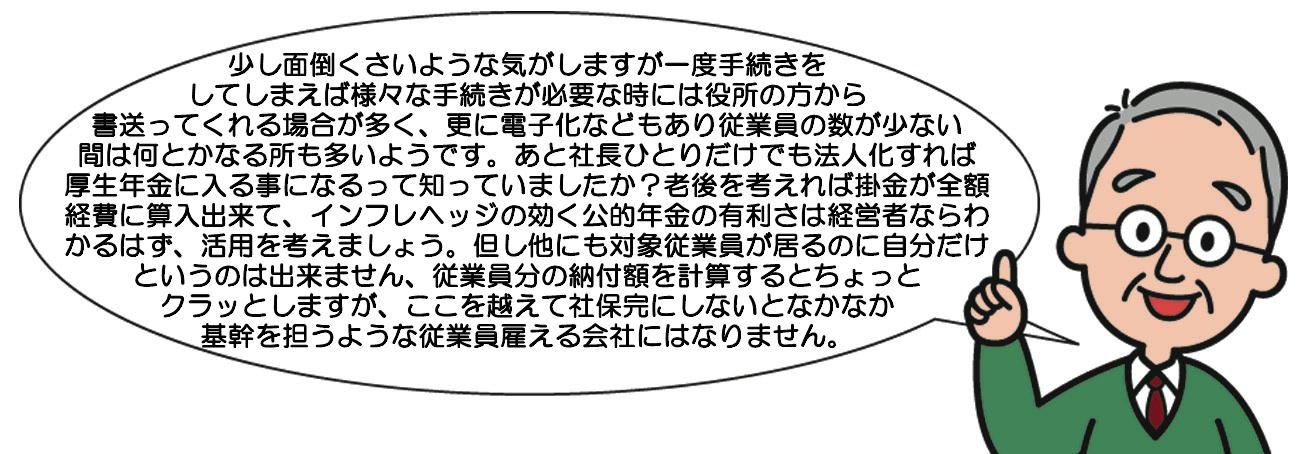
健康保険・厚生年金保険
個人事業の場合で5人未満の事業所は加入の義務がありません、一定の業種では5人以上であっても個人事業の場合は加入義務はありません(どちらも要件を満たし厚生労働大臣の認可をうけた場合は加入できます)法人の事業所ではごく一部の臨時的l雇用の労働者等を除き、原則として通常の労働者の労働日数の3/4以上労働している短時間労働者等も含めて加入の義務があります。(501人以上の大規模事業所では加入義務のある従業員が更に拡大しています)
会社の経営者も加入します、小規模企業の経営者には厚生年金への加入は大きなメリットですが加入するべき従業員を加入させずに経営者だけ加入することは出来ません
なお、厚生年金の 保険料(俗に言う掛金額)も給与額に応じて決まっていますから、掛け金を増やそうとすると給与総額増やすことになります、経営者の給与(厚生年金の保険料納付額の元となる給与)は、当然ですが税負担など全体のバランスをよく考えて決める必要があります。
厚生年金に加入する必要がある場合(健康保険も協会けんぽに加入する場合)は、健康保険・厚生年金保険新規適用届や被保険者資格取得届等の届け出書類を年金事務所に提出します.
「健康保険被保険者証(保険証)」は会社に対して交付されますので従業員の方に引き渡します
労働保険・社会保険への加入や受給手続に関するご相談を承ります