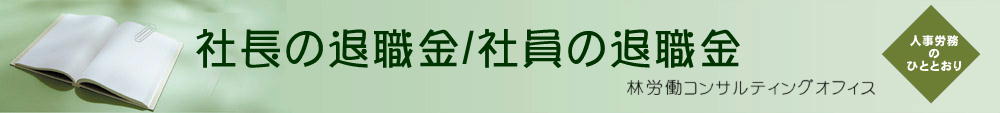退職金規定
創業当初はイメージもピンとこない退職金制度ですが、事業が軌道に乗って来ると従業員の待遇という以前にまず経営者自身の退職金をどうするかという視点から検討する必要が出て来ます。
引退後の生活を考えるという点では社長も従業員も同じことですが、社長の場合はせっかく築いた事業の先行きをどうするのか、後継者を見つけて承継させるのか?誰かに譲り渡すのか?いずれにしても当座の資金が必要になる場合が多く、小規模な企業ほど経営者や役員の退職金をその際の一助とするために、しっかりした退職金規定を定めて置く必要が出てくるからです。
最終的にはかなりの金額を用意する事になる退職金ですが、企業会計的には無理のない金額を少しずつ出資して長い期間運用していくことになります、そのためにはかなり早い時期から計画的に準備をして行くことが必要になります、普段の感覚では、20年後30年後ははるかな将来の事なのですが、こと退職金プランを考える場合には眼前に迫った課題として計画を立てる必要が出て来ます、経営環境が一段落したら将来の経営計画の一部として退職金規定も考えて置くことをお勧めします。
退職金の目標額をどのように設定するかは様々ですが、企業によってはDCや共済では足りず、また経営者の急逝に伴う経営リスクの回避もかねて、各種民間保険を活用するケースも出て来ます、この種の保険商品は種類が多い上に時代とともに新商品に移り変わっていたり、税制が変わっていたりしますので、支払う保険料と受け取る保険金及び受け取りのタイミング、課税の仕組みをしっかり確認して失敗のない運用を心がけてください、
税制上退職金として認められるためには合理的に説明できる金額であることも必要になります、社長や役員の退職金も退職金規定に計算方法を含めてきちんと定めて置いてください。
社員(従業員)の退職金
会社の中に退職金基金を持ち独自に運用するケースと会社外で別個に管理運用するケースがあります
後者のケースでは退職金原資がその時点で従業員等に支払われたと看做して、企業にとっても税制上有利な取り扱いを受けることが出来る等使い勝手が良い制度がある反面、制度上支払いと同時に原資が従業員のものとなってしまう制度では会社に何か不都合な事があつても、取り戻せないという事に強い抵抗を持つ事業主さんもいらっしゃいます。
しかし企業の外に原資を出すことで企業は運用・管理のリスクから逃れる事が出来る一面もあり、何があっても約束した物だけは従業員に渡す事が出来る可能性が高まる他、前述した税制上のメリットも受ける事が出来るのなら要は考え方の問題、決断ひとつと言えるでしょう。
制度導入のための規約制定なども簡便で、小さな企業が利用しやすい中小企業退職金制度、企業規模を問わず近年は退職金・年金に大きなウエイトを占める確定拠出年金のほかにも、退職金制度に使え企業にもメリットのある事を謳う民間保険商品もあります、保険商品は新しいものが登場し古いものが販売されなくなったり、適用税制も変わったりする事もありますので退職金制度に取り入れる時は定期的に確認しておく必要があります。
中小企業退職金共済制度
短時間労働者以外の掛金は月額5,000円~30,000円、積立金は従業員に紐づけされる。
利用できる企業の規模に制限があある。
国や地方自治体からの助成が受けられる。
掛け金は全額損金に算入され、従業員の側でもその段階での課税はされない。
退職金支払い時に会社に赤字が計上されない。
従業員は一部を除き原則として全員加入させる必要がある。
確定拠出年金(企業型DC)
掛金は最大で月額5万5千円までで(企業が他の企業年金も実施していると2.75万円まで)事業主も掛けることが出来る。
拠出された掛け金は拠出された者の資産となるが従業員が勤続3年以内に退職したなどの場合は一定額を拠出した者に返還させる仕組みを持つ。
年金または規約の定めに従い一時金で受け取ることが出来る。会社が拠出する掛け金は全額損金になり、老齢給付を年金で受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金で受け取る場合は「退職所得控除」を受けることが出来るなど税制上も有利な制度。
障害・死亡・脱退等の事情が無い限り60歳まで引き出せなくなること、厚生年金等と違って物価スライドする仕組みをもたないので、大きなインフレ等あった場合は自分の運用で対抗する必要がある点や、従業員の資産運用教育に会社が責任を持つ必要がある点及び運用の指示を誤ると将来の退職金や年金を大きく棄損してしまうことに留意しておく必要がある。
養老保険(福利厚生プラン)
死亡保険金の受取人を従業員の遺族に、満期金の受取りは会社にできる。
保険料の1/2がを損金にすることが出来る。
従業員の退職が早すぎると保険金が少ししか戻ってこない。
満期と退職のタイミングが合わないと大幅な黒字が生じてしまう。
損金算入するためには、少なくとも一定の条件を満たす従業員全員を被保険者にすることが必要で「福利厚生規定」を整備しなければならないなどの注意点があります。
終身保険(福利厚生プラン)/終身がん保険(福利厚生プラン)
終身保険などにも保険料の1/2は損金に出来るハーフタックスプランがあり、退職金の支払い方法にバリエーションがあることを売りにしているものもあるようです。
これらの保険の保険料は概して高額である上、退職時期が早すぎると保険料が少ししか戻らないこともあり、払い戻し率がどうなるのかや税制上の取り扱いについてよく検討しておく必要があります。
社長(役員)の退職金
税制上有利な確定拠出年金や小規模企業共済を利用するほか各種保険を組合せで考えますが、社長の場合は将来における自分や家族の生活プランと言うだけでなく、経営計画の一部として退職金プランを立てることがいっそう強く求められます。
小規模企業共済
会社が掛金を給与として支給すれば損金に計上できる
経営者個人としては掛金は所得税から控除できる
低利の契約者貸付金制度が利用出来る
加入時に小規模企業でないと加入できない。
加入後20年以内に解約すると掛金合計より解約手当金が少ない
掛金を途中で減額すると減額相当分はそれ以降運用されない
確定拠出年金(企業型DC)
労働者向け退職金の所で紹介したDCプランですが、掛金は最大で月額5万5千円(企業が他の企業年金も実施していると2.75万円)まで拠出できるので、経営者の退職金にも組み入れを検討すると良いでしょう
。
逓増定期保険
5~10年目に保険金にちかい解約払戻金を受け取れるが保険料は高額
掛金を一部損金に算入することが出来る(1/2.1/3タイプなどがある.払戻金や期間をよく検討する必要あり)。
退職金支給時に大きな赤字を計上しなくて済む。
契約者貸付が利用できるものもある。
解約払戻金のピークをはずすと保険料が少ししか返って来ない。
解約払戻金を受取ってすぐに退職しないと会社に大きな黒字を計上することになる。
長期平準定期保険
20~30年かけて退職金の準備をするのに向いている。
退職金準備に使う前半6割の期間で1/2を損金に計上できる。
退職金支給時に大きな赤字を計上しなくて済む。
解約払戻金のピークはわりと長く続くので退職金支払いのタイミングと合わせやすい。
契約者貸付が利用できるものもある。
解約のタイミングが早すぎたり遅すぎたりすると払戻金は減る。
解約払戻金を受取ってすぐに退職しないと大きな黒字を計上することになる。
長い保険機関が前提となるので、解約返還金のピークで退職金を受け取るためには、後継者を失念せずにピーク以前に見つけて置くなどの計画性が必要。
生活障害補償定期保険
死亡だけでなく生活障害状態でも保険金が支払われる、解約タイミングによって保険料の7~8割が返ってくる、保険料は高額。
退職金の資金をある程度積立ながら保険料を全額損金に計上できる。
解約払戻金のピークは長く続くのでタイミングは合わせやすい。
高額な保険料が会社のキャッシュフォローを圧迫しないか検討が必要。
ピークで解約しても、良い条件の場合で払った保険料の8割程度しか返って来ない 。
掛金は全額損金にはなるが、解約返還金はすべて益金となって課税されるため、解約払戻金を受取ってすぐに返還金に見合う退職者を出さないと、大きな黒字を計上する破目になる。
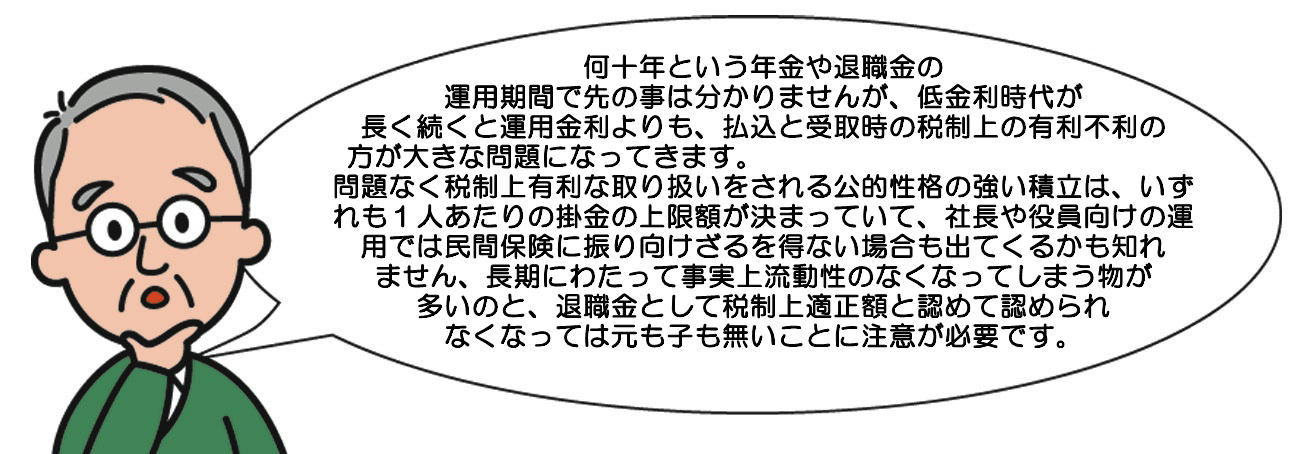
退職金についての各種ご相談を承ります