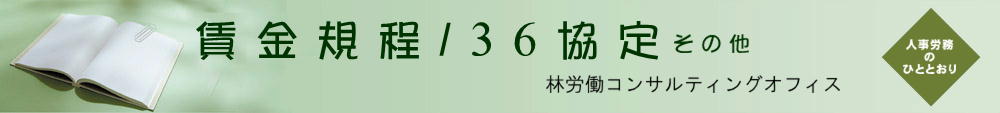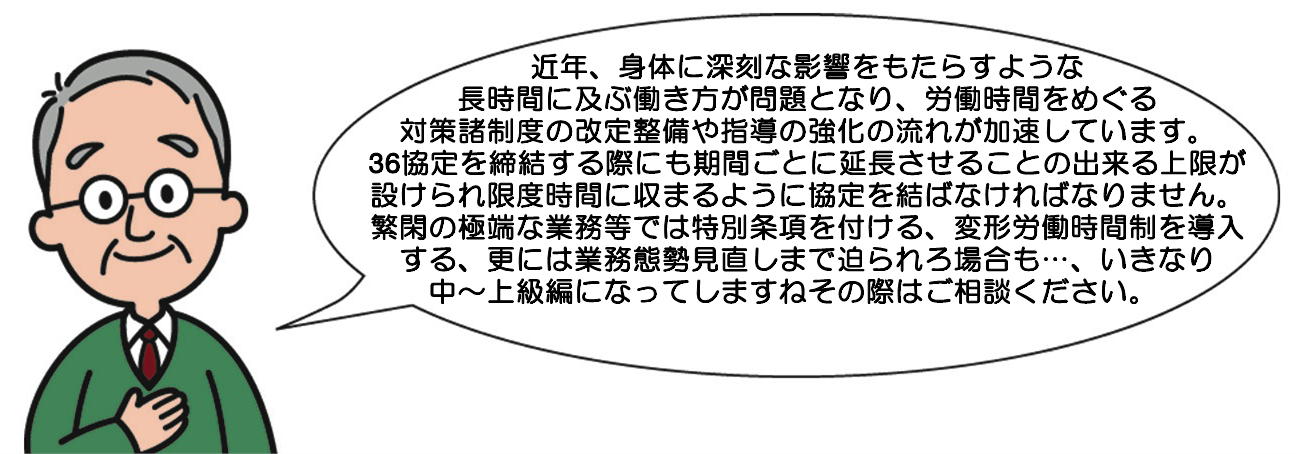就業規則のうち「賃金の決定、計算、支払いの方法、賃 金 の 締め切り・支払いの時期に関する事項」等のの部分だけを別規定にしたのが賃金規程です、全てをひとまとめにしても良いのですが、取り決めて置く事項や改定も多いため別に作成する事が多くなっています。こうした規定も就業規則として定める事が求められている部分は就業規則の一部になりますので、10人以上の事業所では従業員の過半数を組織する労働組合のある時はその労働組合、それ以外の場合は従業員の代表する者の意見聴取をしたうえで労働基準監督署に届け出ることになります。
おおまかに賃金規程に記載すべき内容は下記のとおりです。
●適用範囲 正社員とパートタイマーなどに異なる規定が適用されろ場合は適用範囲を明示します。
●賃金の支払い方法 通貨で直接全額払いが原則ですが振込等による場合は手続き含め記載します。
●賃金の計算期間、支給日 賃金締切日と支払日を決めておきます。
●賃金の控除 税や社会保険料、労使協定により賃金から控除することにしたものの取り扱い
この他、欠勤・遅刻・早退などの場合等の賃金の取り扱いや、諸手当、時間外労働の割増賃率等の
事項、退職金や賞与の定めを置く場合、従業員に負担させるものがある場合、減給の制裁を行うな
どの制度を定める場合はそれらに関する事項も記載します。
賃金支払い5原則(労働基準法24条)に反する賃金支払いは原則として出来ません
①通貨払いの原則 国内で強制的に通用する貨幣で払わなければなりません
②直接払いの原則 賃金を直接労働者本人に支払わなければなりません
③全額払いの原則 賃金の一部を差し引いたりは出来ません(労使協定による一部控除は可)
④毎月一回以上払いの原則 賃金は少なくとも月一回以上支払わなければなりません。
⑤一定期日払いの原則 賃金は毎月一定の期日を定めて支払わなければなりません
※労働者の同意を得た 上で、労働者が指定する銀行等の金融機関の口座に振り込む場合は上記直接 払いの原則に違反しないとされています。
賃金規程で賃金の計算期間をあまり短く設定すると、後になって諸控除や手当などの計算が間に合わなくなったりします、経営を始めた頃は見当をつけづらい所ですが、後々困った事態にならないようにスケジュールには余裕を持たせた方が良いでしょう
何時でも法定労働時間である1週40時間、1日8時間(原則)で仕事が終わるのなら問題はありませんがそれが難しければ、業務繁忙時等には残業手当を払ってでも法定労働時間を越えて働いて貰う必要が出て来る事があります。このため36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)は比較的早い時期から結ぶ必要の出てくる協定のひとつですから、独特な略称(さぶろくきょうてい)も含めて覚えておくと良いでしょう。
36協定は従業員の過半数を組織する労働組合又は従業員の過半数を代表する者との間で書面による協定を締結し、職場に周知すると共に別途「時間外労働・休日労働に関する協定届」により労働基準監督署に届け出る必要があります。
36協定で定めるべき事項
①時間外または休日労働をさせる必要のある具体的事由
②業務の種類
③労働者の数
④1日及び1日を超える一定の期間について延長することが出来る期間、または労働させるこ とが出来る休日
⑤有効期間(その労使協定が労働協約である場合を除く)
上の従業員の代表者は課長などの管理監督者であってはならず、きちんとした選挙等でで選ぶ必要があります。
36協定延長することのできる延長時間の限度については、36協定締結の前に必ず最新のものを都道府県労働局や労働基準監督署で入手するようにしてください。
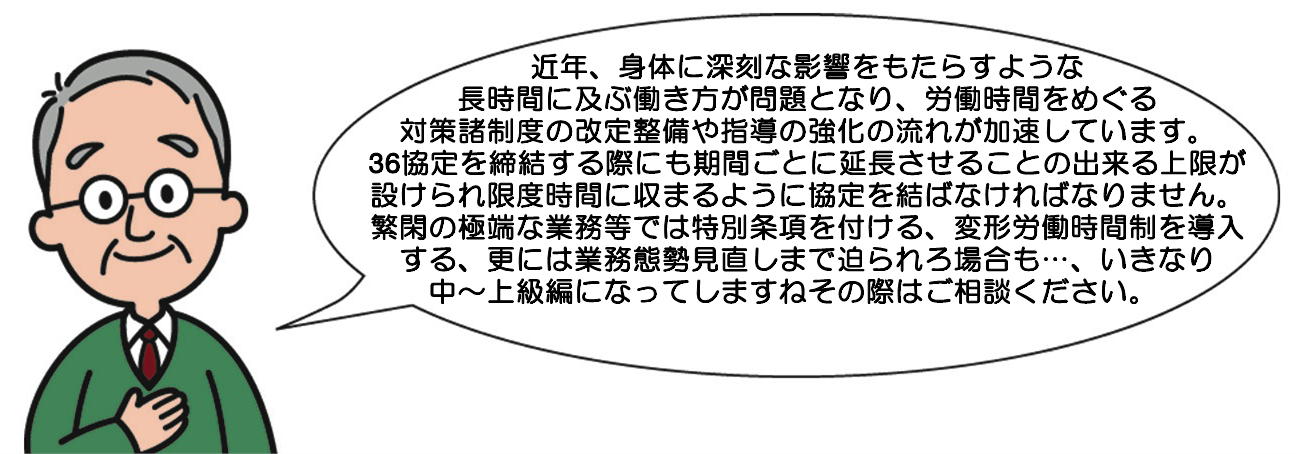
2020年からは
中小企業でも時間外労働は一部の業種を除き特に繁忙な時期であっても月に 100時間未満で、かつ複数月平均で80時間以内にしなければならず、更に月45時間を超える残業をさせる事が出来るのは年間6か月までとされました。
この基準に違反した企業には、時間外手当の支払いとは別に罰金が科されることになりますので、受注の都合等で長時間労働が発生しやすい会社は注意が必要です。
上記のの時間外・休日労度に関する協定(36協定)は従業員の過半数を組織する労働組合と(無い場合は従業員の過半数を代表する者と)の間で書面による協定を締結し労働基準監督署に届け出る
必要がある協定の代表格ですが、このほか、繁閑のある事業などの場合に締結する(1週間単位・1月単位・1年単位)の変形労働時間制の協定など届け出を要する労使協定はたくさんあります、必要な場合は協定を結び職場に周知するとともに、労働基準監督署に届け出ることになります。
※一か月単位の変形労働時間制をの必要事項を就業規則ををもって定めた場合を除きます。
労使協定書の作成し、労働基準監督署に届け出を要する協定の例(36協定以外の例)
①1年単位の変形労働時間制に関する協定
②1か月単位の変形労働時間制に関する協定(就業規則で定めた時は届け出不要)
③1週間単位の非定型的変形労働時間に関する協定
④事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する協定(所定労働時間以内は届け出不要)
⑤専門・企画業務型裁量労働に関する協定
⑥預貯金(社内預金)管理に関する協定
その他労使協定書の作成を要するものの例(届け出は不要)
●賃金を一部控除する協定
●フレックスタイム制に関する協定
●一斉休憩の除外に関する協定
●年次有給休暇の計画的付与に関する協定
●年次有給休暇中の賃金に関する協定
●育児休業・介護休業の適用除外者に関する協定
●高年齢者の再雇用に伴う基準の設定
全部一度に労使協定を結ぶ必要はなく、必要の都度従業員代表との間で協定を締結して、届出の必要なものは労働基準監督署に届け出れば良いのです。
賃金規程や労働時間に関するご相談・協定書の作成などを承ります
●36協定や賃金規程等に関するご相談、これに付随する協定書の作成、および改 定に関するご相談を承っております。
●繁閑のある事業所などが労働基準監督署に届け出て行う変形労働時間制(1週間 単位・1月単位・1年単位)のご相談や、各種裁量労働制の導入など多岐にわた る労働時間管理制度のご相談なども承ります。